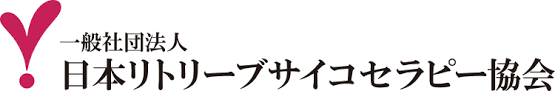こんにちは
東京・千葉で活動しております、心理セラピストの野沢ゆりこです。
連日暑い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。
お子さんが夏休みで、夏の行楽シーズン、帰省シーズンで子供のお世話が増え、何かと忙しい日々を過ごされている親御さんも多いのではと思います。 今日は、実際に耳にした、中学1年の息子のラインを盗み見て、息子の動向をチェックしては一喜一憂するママの事例について、その心理的背景を書きたいと思います。
事例紹介
ある40代のママは、中学1年の息子のLINEをこっそりチェックし、交際中の同級生とのやりとりまで細かく把握していました。
彼女は息子の交際中の子に対する気持ちや接し方が気になってしかたがないようで、「うちの息子、○○ちゃんにこんなこと言ってたの」と、その内容をママ友に逐一話しています。息子の言動はママ友たちに筒抜けになっているのです。

その女性にとっては、「母親なのだから当たり前」であり、全く悪気もないようでした。
ですが、周囲の人からみると少し行き過ぎた干渉に映ります。息子の立場だったらどうでしょう?嫌ですよね?
あなたは、母親と子供、どちらの立場でこの事例を捉えますか?
子どもの立場なら嫌だけど、母親だったらチェックするかもしれない…そう思うあなたは、コントロール欲求が強いタイプ、そして過干渉になりやすいタイプだといえます。
心理的背景
1・境界のあいまいさ
親子には本来、心理的な境界があります。たとえ血がつながっていても別の人間です。
しかし、子供を「自分の分身」「自分の手足の延長上」のように感じると、その境界が薄れ、子供の世界を自分のテリトリーのように扱ってしまうことがあります。
2・不安とコントロール欲求
「知らないこと」が不安で、すべてを把握したくなるのは自然なことです。思春期は子供が親から距離を取り始める時期なので、不安や寂しさ特に強まります。
3・自己同一化(子供を通して自分を生きる)
親が自分の願望や未完了の感情を子供に投影し、「自分の人生の延長」として捉えることで、過剰な介入が起こりやすくなります。
・過去に自分が傷ついた経験があるから、子供には傷ついて欲しくない。
・過去に自分が失敗したことがあるから、子供には失敗し欲しくない。
・過去に自分の望みが叶わなかったから、自分に代わって子供に叶えて欲しい。
このように、親の欠乏感、不足感、心の傷が子供への干渉、過剰な介入の原因になることがあります。
「全部知りたい」「何でも報告してほしい」気持ちの正体
知りたい、報告して欲しい、把握しておきたい、これらの欲求は、決して悪意ではなく、愛情の裏返しです。
・親自身が、安心したい気持ち
・親自身が、つながりを失いたくない気持ち
・親自身が、見守っていることを形にしたい気持ち
これらが重なって「全部知りたい、話してほしい」という形で表れます。
ですが、我が子であっても、人のことを100%知ることは不可能です。
これは、夫婦であっても、親友であっても、同じではないでしょうか。
愛しているから、大好きだからと、何度も会話を重ね、どんなに言葉を尽くしたとしても、分かり合えない部分、触れられない部分はあると私は思います。
過干渉の将来のリスク
こうした干渉は、短期的には親の安心感につながりますが、長期的には信頼を損なう危険があります。
・子供が秘密主義になる
・嘘をつくようになる
・自立の時期を逃す
・失敗の経験、成長の機会を奪う 親子の関係は、「監視」よりも「信頼」でこそ長く続くものです。
子どもを安心して見守るためのステップ
では「干渉し過ぎる」ママから、「安心して見守る」ママになるためにはどうしたらいいでしょう。
1・自分の気持ちに気づく
「なぜそんなに知りたいのか?」と自分を責めたりするのではなく、「私は不安なんだ」「もっとつながっていたいんだ」と自覚することから始めます。
2・境界を学ぶ
「親が知っていいこと」と「子供が自由に持つべき世界」を意識的に分けること。思春期は、前から引っ張るのではなく、後ろから支える時期なのです。
3・信頼を育む会話
詮索ではなく、心(感情)に触れる質問を増やします。
「今日はどうだった?」「何をしたの?」よりも、「どんなことが楽しい?」「それでどう感じたの?」の方が子供は話しやすいのです。
4・応援していることを言葉にする、姿勢や態度で示す。
「あなたのことを信じているよ」「大切に思っているよ」という言葉や態度は、子供にとって何よりの安心材料になります。
5・自分の人生を満たす
子ども以外に夢中になれる趣味や人間関係を持つことで、子供に過度に依存しないバランスが取れます。
まとめ
思春期の子供を持つ親にとって、「何でも話してほしい」と願う気持ちは自然な愛情です。
そして、子供側の「親には秘密にしておきたい」という気持ちも自然な感情です。
大切なことは、「信頼は情報の量ではなく、関係の質から生まれる」ということです。
「あなたを信じて見守る」という姿勢こそが、子供にとって最大の安心であり、親にとっても大きな愛情の形です。
あなたがもし、この事例のママのように、子供をコントロールしたい、何でも知りたいと思うなら、そして、「子供以外の自分の世界をぜひ作って下さい」と言われて、戸惑いを感じるなら、ご自身の不安や孤独感、欠乏感や不足感に向き合うことをおすすめします。
子どもと長くいい関係でいるために。子育てはいつか終わる時がきます。その時に燃え尽きたり、空の巣症候群に陥らないために。あなたの人生が充実したものになるために。
カウンセリングやセラピーがお力になれると思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。(野沢ゆりこ)

コラム担当者の紹介:協会認定セラピスト 【千葉県】野沢ゆりこ